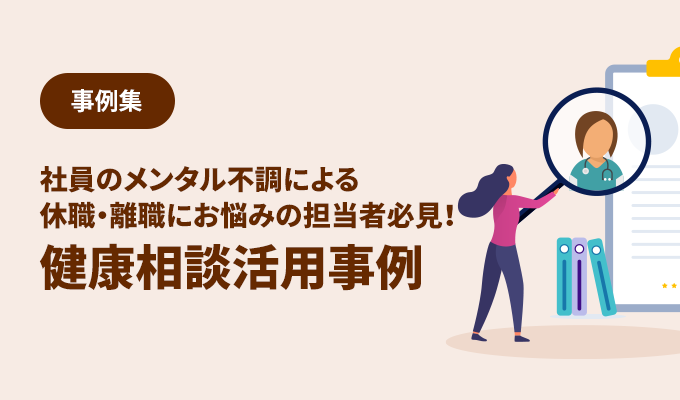人事部門に寄せられる社員からの相談は多岐に渡ります。社内制度や手続きにまつわる質問に加え、「休職したい」「体調が優れない」「癌になってしまった」など、本人の健康やメンタルにとって、あるいは本人の人生そのものにとって、非常に深刻な相談も少なくありません。このような相談に対して、人事側では産業医や産業看護職と連携をとりつつ、正確でスピーディな対応が求められます。しかしながら、産業医と連絡がつかない、やりとりに時間がかかってしまうなど、決して迅速に対応ができているとは言えない状況があります。親身になって相談に乗りたい、なんとかしてあげたいと願う一心で、対応に充分な医療知識や専門性を持ち合わせない中、人事担当者がひとりで抱え込むケースも少なくありません。このような困難な状況は、一体どうすれば改善することができるのでしょうか?本稿では、中小企業のひとり人事や少人数の人事部門で起こり得るこういった事態への打開策として、「社員の悩みを人事が抱え過ぎない仕組みづくり」について詳しく解説致します。また後半では、ひとり人事でも健康経営優良法人を目指せるまったく新しい健康相談窓口の形についてもご紹介させて頂きます。
健康相談 活用事例
リモートワークや組織変化に伴い、社員のメンタル・体調不良や、それによる休職・退職の増加を未然に防ぐ施策として、ONLINE健康相談室をご提案しています。活用事例をまとめました。
社員の悩みを人事が抱え過ぎない仕組みづくり3つのステップ
社員の相談を分類することから始める(第1ステップ)
社員からの悩みや相談を人事が抱え込まない仕組みをつくる上で、第一にやるべきことはいま寄せられている相談をジャンル別に分類することです。まず人事担当だけで答えられるものと、そうでないものに分類します。後者には医療知識や専門性が必要なもの、有資格者でないと対応できないものがあり、それらは基本的には外部相談員(EAP)や産業保健スタッフ(産業医・産業看護職)へ切り出していくことを考えましょう。下図では人事部門によくある相談を合計6ジャンルに分類しています。あなたの会社では、社員からどのような相談が寄せられているでしょうか?一度棚卸しをして、ジャンル分けしてみて下さい。

ジャンル別に相談要員を検討する(第2ステップ)
ジャンル分けができれば、次のステップとして各々のジャンルに対応可能な人物を検討していきます。例えば以下のような割り当てを考えることができます。これに関しても具体的にあなたの会社で割り当て可能な体制を考えてみましょう。



ジャンル別に対応要員が決まれば、各々のジャンルでどれほどの相談ボリュームがあるか、具体的にどんな相談が寄せられているか確認し、必要な人材やサービスを検討しましょう。
相談窓口の体制を整える(第3ステップ)
現在寄せられている相談内容と対応要員が決まれば、最後に相談窓口の体制を整えていきます。体制は一次相談窓口と二次(専門)相談窓口の二段構えで構築することをお勧めします。一次窓口では実にさまざまな相談が寄せられます。緊急対応を要するもの、他部署や外部機関との連携が必要なもの、稀ではありますが自傷他害のケースなど、相談内容には要配慮個人情報が含まれることも多いため、一次窓口には人事部スタッフが入るようにします。性差による特有の相談が寄せられることも配慮して、男女1名ずつ、計2名体制で担当者を立てましょう。一次窓口では社員から受けた相談内容をヒアリングすることに徹し、必要に応じて二次専門窓口へと取り次ぎます。正確でスピーディな対応が求められるため、予め対応マニュアルとレポートラインを作っておくことが極めて重要です。

迅速正確で開放された相談窓口をつくる3つのポイント
敷居の高さ、相談しづらさをどう取り除くか?(アクセスビリティ)
人事への相談は時に社員を躊躇させることがあります。躊躇させる原因は主に2つで、心理的弊害と物理的弊害にわけることができます。前者は「相談すれば人事評価に影響が出るのでは?」「相談内容は誰にどこまで伝わってしまうのか?」といったものです。こういった心配を払拭するためにも、公平性と秘匿性が十全に確保されていることを全社員に徹底周知することが重要です。一度きりの周知ではなく、社内のあらゆる媒体を活用し、繰り返し発信を行っていきましょう。情報認知に関する有名なスリーヒット理論では、同じ情報には最低3回接触しなければ認知されないと言われています。一度きりのお知らせでは到底周知には至らないのです。
相談を躊躇せる物理的弊害もできる限り取り除きましょう。相談窓口へアクセスしやすい環境を整えます。複数拠点ある組織では対面相談が難しい場合があるため、電話やビデオ会議などオンラインを活用した相談窓口を設けます。なお、ビデオ会議による相談には専用の個室や会議スペースを設け、安心して話せる空間を作っておくことも社員の安心感に繋がります。相談可能な時間帯はできる限り幅を持たせましょう。社員の職種によっては特定の時間帯や曜日しか相談できない場合もあります。

複雑に絡み合う悩み相談にはどう対処すべきか?(正確性)
相談によっては問題が複雑に絡み合うものも少なくありません。相談者自身が一体何が問題なのか把握できておらず、要領を得づらいケースもしばしばあります。こういった場合、一次相談窓口における重要な役割は、まず情報整理をすることです。相談者の現状がどうなっていて、何が問題かを特定したのち、それを相談者と認識合わせすることです。これには傾聴スキルが欠かせません。一次窓口には傾聴スキルの高い担当者を立てることを意識しましょう。また、ヒアリングシートや面談記録シートを用意しておくことで、対応に一定のクオリティを保つことができます。情報の整理や他関係者への情報共有にも役立つためおススメです。なお、相談者の中には「ただ話を聴いてほしい」というだけの方もいます。そのような場合でも、やはり傾聴スキルは大切で、腰を据えてじっくりと話を聴くことが担当者には求められます。
一次窓口担当者の時間的リソースを最優先で確保する(迅速性)
社員から来る相談には緊急を要するものも多く、スピーディな対応が求められます。相談申請があった際に、できる限り迅速な面談設定ができるよう、一次窓口に立つ担当者の時間的リソースは柔軟に確保できる体制を整えておきましょう。窓口担当者とはいえ、他の人事業務と兼任することが多いものです。急な相談申請があった場合でも、周囲のサポートや理解があれば、迅速に相談対応に入れます。

以上、人事が社員の悩みを抱え込むことなく、他スタッフや産業保健スタッフ、外部機関と連携して、組織で円滑に健康相談窓口を運用する方法をお話してきました。以降は、「そうは言ってもイチから体制を整えていくのは難しい」「時間も予算もそこまで割けない」という方のために、ひとり人事でもこれ以上工数を増やすことなく、健康経営優良法人を目指せる新しい健康相談窓口の形をご紹介したいと思います。
ひとり人事でも健康経営優良法人を目指せる新しい健康相談窓口の形とは?
主に中小企業のひとり人事や少人数の人事部門が健康相談窓口を立ち上げる際、ボトルネックは現在の業務で手いっぱいということです。人事の負担を減らしながら、社員から頼られる健康相談窓口を作るはずが、その構築ノウハウや知見が不足している上、着手する余裕すら与えられないことが大きな課題と言えます。そこでこの解決策として、弊社パソナが提供する「ONLINE健康推進室」をご紹介したいと思います。
「ONLINE健康推進室」とは、オンライン上に貴社従業員専用の健康相談窓口を作れるサービスです。貴社従業員の方は、LINEアプリからチャットでいつでもONLINE健康推進室にアクセスでき、弊社パソナ所属の看護師や保健師など専門スタッフに健康相談をすることができます。LINEによるインターフェースは飛躍的にアクセスビリティを向上させます。またプロの産業看護スタッフが対応するため、複雑な相談にも正確かつ迅速に応じることができます。すでに導入される企業様では、通常の外部相談窓口に比べ相談率が10倍になったというデータが出ています。相談の物理的ハードル、心理的ハードルを下げることで、従業員の潜在的な健康課題を早期に発見解決することができます。

また、ONLINE健康推進室の仕組みを使えば、産業看護職による健康面談の実施も全社員に対してスムーズに実施できます。もちろん面談は弊社パソナに所属するONLINE健康推進室専任の産業看護スタッフが行います。貴社スタッフが自ら面談に入ったり、新たに産業看護職を採用する必要は一切ありません。担当者ひとりでも全社員の健康面談を難なく運用することができます。毎年手が回らなかった健診後の保健指導、支店・支社での産業保健面談、産業医だけでは対応しきれない健康相談など、一年を通じて必要な面談業務の計画から実行、フィードバックまで、すべてONLINE健康推進室で完結することができます。

ONLINE健康推進室は、ひとり人事や少人数の人事部門でも、大手企業や健康経営優良法人と同じ高い水準で健康相談窓口を作れるサービスです。上記以外にも産業保健や健康経営に役立つさまざまな機能が備わっています。ONLINE健康推進室の具体的な仕組みや他にできること、導入事例、ご利用プランなどは以下の資料で詳しく紹介しております。ご興味のある方は今すぐダウンロードください。

健康経営支援サービスのご紹介
健康経営に取組む目的や課題を共に明確化し、「産業保健の法令対応・基盤固め」から「健康経営の推進・カルチャー醸成」に至るまで伴走サポートいたします。
健康経営の取り組みについて悩んでいる企業ご担当者様は、ぜひご覧ください。