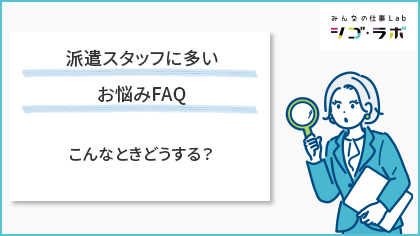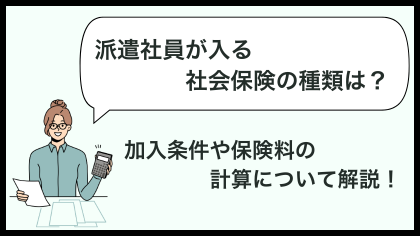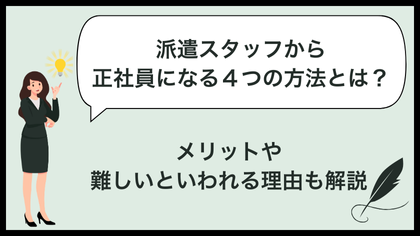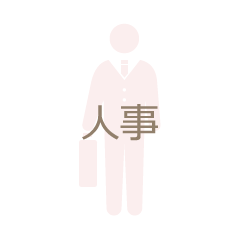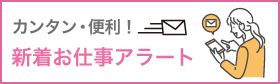派遣スタッフは健康保険に加入できる?
条件やメリット・切り替え方法を解説
更新日:2025年10月14日
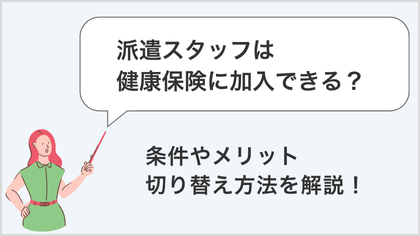
「健康保険って自分も入れるの?」「扶養から外れるってどういうこと?」派遣スタッフとして働いている方の中には、健康保険について疑問を感じている方もいるのではないでしょうか。
本記事では、健康保険の加入条件・加入メリット・手続きや派遣契約終了後の切り替え対応までをわかりやすく解説し、家事・育児や介護と両立しながら働きたい方の不安や疑問を解消していきます。
目次
派遣スタッフは健康保険に加入できる?

派遣スタッフが健康保険に加入できる条件と手続きの流れについて紹介します。
健康保険への加入義務がある派遣スタッフの条件
派遣スタッフも一定の条件を満たせば健康保険に加入できます。
具体的には、厚生年金保険の被保険者数が常時51人以上の従業員がいる企業で働いていて、以下の条件を満たす場合は、健康保険を含む社会保険の加入対象となります。
- 所定労働時間が週20時間以上30時間未満
- 所定内賃金が月額8.8万円以上
- 2ヶ月以上の雇用の見込みがある
- 学生ではない(休学・定時制・通信制の場合は対象)
参考:厚生労働省「社会保険適用拡大|対象となる事業所・従業員について」
所定内賃金は基本給と固定手当のみが対象で、残業代や交通費・賞与は含まれません。
また、当初の契約では週20時間未満であっても、業務の都合などにより、実際の勤務時間が2ヶ月連続で週20時間以上となり、その後も同様の勤務が見込まれる場合は、3ヶ月目から健康保険の加入対象となることがあります。
派遣スタッフの社会保険については、以下の記事で詳しく解説しています。
加入手続きは派遣元が実施
派遣スタッフの健康保険加入手続きは、派遣先ではなく雇用契約を結んでいる派遣会社(派遣元)が行います。
派遣会社は雇用契約開始から5日以内に、社会保険の加入手続きを行う義務があります。
派遣スタッフが健康保険に加入するメリット

派遣スタッフが健康保険に加入することで得られるメリットは、以下のとおりです。
- 保険料の自己負担額が抑えられる
- 一定の要件を満たす場合、傷病手当金や出産手当金が受けられる
それぞれのメリットについて解説します。
保険料の自己負担額が抑えられる
派遣スタッフが健康保険に加入すると、保険料の半分を派遣会社が負担するため、国民健康保険に全額自己負担で加入する場合に比べて、負担が軽くなることがあります。
国民健康保険は加入する家族の人数に応じて保険料が増える仕組みですが、健康保険では扶養家族を追加しても保険料は変わりません。そのため、扶養する家族が多い世帯ほど、国民健康保険と比べて保険料の総額に差が出やすく、結果として保険料の負担を抑えられる可能性があるのもメリットといえるでしょう。
一定の要件を満たす場合、傷病手当金や出産手当金が受けられる
派遣スタッフが健康保険に加入している場合、各要件を満たしていれば病気やケガ、出産といった理由で働けなくなったときに傷病手当金や出産手当金を受け取ることができます。
傷病手当金は、業務外の病気やケガで就労できなくなった際に支給され、金額は給与の約3分の2です。最長1年6ヶ月にわたり生活を支える仕組みで、契約期間が限られる派遣スタッフにとっては経済的・心理的な安心材料となります。
また、出産手当金は出産による休業中に支給されます。支給の対象期間は以下の通りです。
| 項目 | 対象期間 |
|---|---|
| 産前 | 出産予定日の42日前 (多胎妊娠の場合は98日前) |
| 産後 | 出産日の翌日から56日後まで |
| 合計 | 最大98日間 (多胎妊娠の場合は最大154日間) |
支給額は給与の約3分の2で、「出産育児一時金(原則50万円)」との併用も可能なため、妊娠・出産を控えた方にとって大きな支えになります。これらの制度は国民健康保険にはないため、派遣スタッフが社会保険に加入する大きなメリットといえるでしょう。
支給要件の詳細は、派遣会社または「協会けんぽ」などにあらかじめ確認しておくと安心です。
派遣スタッフが健康保険に加入する際の注意点

派遣スタッフが健康保険に加入する際に知っておくべき注意点は、以下のとおりです。
- 保険料の負担により手取り額が減る場合もある
- 扶養から外れる可能性がある
それぞれの注意点について解説します。
保険料の負担により手取り額が減る場合もある
派遣スタッフが健康保険に加入すると、健康保険料や厚生年金保険料がお給料から差し引かれるため、手取り額が減ったように感じられることがあります。しかし、社会保険に加入することで、一定の要件を満たせば傷病手当金や出産手当金などの給付を受けられるため、病気や出産で収入が減っても生活を支えられる仕組みがあります。
手取り額の変化に戸惑うこともありますが、長期的に安心して働けることがメリットといえます。
社会保険料の総額や標準報酬月額については、以下の記事で詳しく解説しているので、ぜひご確認ください。
扶養から外れる可能性がある
配偶者の健康保険に扶養として入っている場合、派遣会社の健康保険に加入すると自動的に扶養から外れることになります。派遣スタッフ自身が健康保険の「被保険者」となると、他の健康保険で「被扶養者」として扱われなくなるためです。
また、配偶者の勤務先で「家族手当」や「配偶者手当」などが支給されている場合、扶養から外れることによって支給対象外になる可能性もあります。
扶養から外れる前には、保険料の自己負担額や税制上の控除の影響をふまえて家計全体で試算し、社会保険に加入することで得られるメリットとバランスを見極めることが大切です。
派遣スタッフが健康保険に加入する手続き

派遣スタッフが健康保険に加入する際の、具体的な手続きの流れについて紹介します。
派遣会社に提出する必要書類
派遣スタッフが健康保険に加入する際は、派遣会社にマイナンバーと基礎年金番号を提出します。
扶養家族を追加する場合は、住民票や所得証明書、雇用保険受給資格者証なども必要になる場合があります。
派遣会社によって独自のフォーマットが用意されていることもあるため、登録時の案内を確認することが重要です。
派遣スタッフが行う手続き
健康保険の加入手続きは派遣会社が行うため、派遣スタッフが直接年金事務所や保険者に手続きに行く必要はありません。
自身で行うのは主に、マイナンバーカードを健康保険証として使うための申し込みで、マイナポータルやコンビニATMで簡単に行えます。
扶養家族がいる場合は、国民健康保険の脱退手続きや前保険証の返却も忘れずに進める必要があります。
資格確認書が届いた際は内容を確認し、誤りがあれば派遣会社に早めに連絡しましょう。
マイナ保険証の利用を設定しておけば、資格確認書が手元に届く前でもスムーズに受診でき、医療費の限度額適用にも対応できます。
派遣契約終了後の健康保険の切り替え

派遣契約が終了した際の健康保険の切り替えには、以下の3つの選択肢があります。
- 国民健康保険へ切り替える
- 任意継続被保険者制度を利用する
- 家族の健康保険の扶養に入る
それぞれの選択肢について詳しく解説します。
国民健康保険へ切り替える
派遣契約が終了すると、健康保険の資格を失うため、国民健康保険に切り替える必要があります。退職日の翌日から14日以内に市区町村役場で手続きを行うのが原則です。
必要書類は資格喪失証明書やマイナンバーカード、印鑑などで、自治体によって細かな違いがあります。また、保険料は前年の所得や世帯人数で決まり、自治体ごとに金額が異なります。
手続きが遅れると、医療費を一時的に全額自己負担することになる恐れがあるため、早めの行動が大切です。
任意継続被保険者制度を利用する
任意継続被保険者制度を利用すれば、加入していた健康保険を最長2年間続けられます。
条件は「資格喪失日の前日までに2ヶ月以上の被保険者期間があること」で、資格喪失日の翌日から20日以内に「任意継続被保険者資格取得申出書」の提出が必要です。
保険料は全額自己負担になりますが、扶養家族はそのまま利用継続をすることができます。
家族の健康保険の扶養に入る
派遣契約終了後、家族が健康保険に加入している場合は、年収が130万円未満であれば、扶養に入ることができます。
ただし、被扶養者の収入には、雇用保険の失業等給付、公的年金、健康保険の傷病手当金や出産手当金も含まれますので注意が必要です。
扶養に入る手続きでは、離職票や雇用契約書など収入を証明する書類を提出し、家族の勤務先を通じて申請します。審査には1〜2週間ほどかかるのが一般的なので、早めの準備を心がけましょう。
派遣スタッフの健康保険に関するよくある質問(FAQ)
保険証が届くまでどのくらいかかりますか?
派遣会社が資格取得届を提出してから、2週間ほどで資格情報のお知らせが届きます。
※2024年12月以降は紙の保険証の新規発行が停止され、資格確認書と資格情報のお知らせでの対応となっています。
医療機関を受診する予定がある人は、派遣会社に確認し、マイナンバーカードを健康保険証として使えるよう事前に申し込んでおくと安心です。
保険証が届く前の受診方法は?
保険証が手元にない間でも、マイナンバーカードを保険証として利用できる医療機関なら3割負担で受診可能です。資格情報が反映されていない場合は、資格情報のお知らせや資格確認書を併用すれば問題ありません。
資格情報のお知らせや資格確認書が手元にない場合は、一旦10割負担の金額を支払い、後日療養費申請で差額を払い戻してもらう方法があります。事前にマイナ保険証の申し込みを済ませておけば、受診時の不安を減らせるでしょう。
健康保険にはいつから加入するの?
4つの条件(所定労働時間が週20時間以上・月収8万8,000円以上・2ヶ月超の雇用見込み・学生でないこと)を満たせば、雇用契約開始日から健康保険への加入が可能です。
短期派遣でも健康保険に入れますか?
短期派遣でも2ヶ月と1日を超える見込みがあれば、健康保険に加入できます。
また、契約終了後1ヶ月以内に次のお仕事がスタートすれば、健康保険の継続も可能となる派遣会社もあります。
そのため、健康保険の加入対象になるかどうかは、派遣会社に確認することが大切です。
派遣スタッフは条件を満たせば健康保険に加入できる

派遣スタッフも一定の条件を満たすことで、健康保険に加入できます。
健康保険に入ると、医療費の自己負担が軽くなるだけでなく、病気やケガ、出産といった万一のときにも条件を満たせば手当金が支給されるため、安心して働き続けることが可能です。加入条件や手続きに疑問があるときは、派遣会社に相談しましょう。
パソナでは一定の就業条件を満たした場合に、健康保険にご加入いただいており、相談窓口も設置しているので安心して働いていただけます。お仕事をぜひチェックしてみてください。