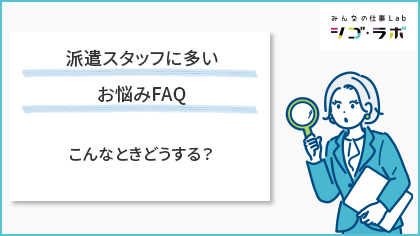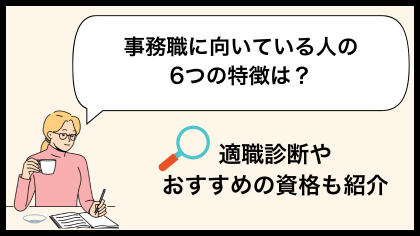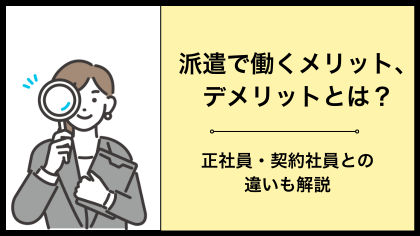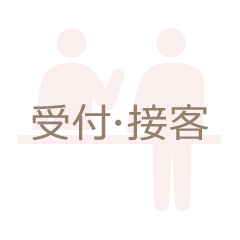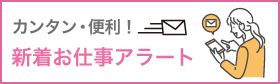派遣社員が入る社会保険の種類は?
加入条件や保険料の計算について解説
更新日:2025年8月20日
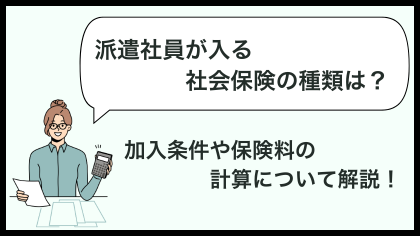
派遣社員として働く中で、「社会保険にはいつから入るの?」「扶養から外れたらどうなるの?」と不安を感じていませんか。
保険料の負担や手取り収入の変化、年金や医療保障との関係など、制度が複雑でわかりづらいと戸惑う方もいるでしょう。
この記事では、派遣社員の社会保険の種類や加入条件、加入するメリットや注意点などを解説します。
※本記事の内容は掲載した時点での情報です。掲載した時点以降に変更される場合もあります。
目次
社会保険とは

社会保険は、病気やけが、失業、老後などに備えるための公的な制度で、従業員が安心して働ける環境を提供するためにあります。
一定の条件を満たす場合に、雇用形態に関わらず加入となります。
また、2024年10月から社会保険の適用が拡大され、加入対象者の幅が広がりました。
派遣社員の場合は、派遣元(雇用主)である派遣会社の社会保険に加入します。
社会保険の種類と加入条件

派遣社員が加入できる社会保険の種類と、それぞれの加入条件について詳しく紹介します。
健康保険
健康保険に加入すると、医療費の自己負担が原則3割に軽減されるほか、一定の条件を満たせば、病気やけがで働けない場合に「傷病手当金」として給与の約3分の2が支給される制度も利用できます。
2024年10月からは、健康保険の加入対象となる範囲が広がりました。これまで対象となっていなかった従業員51人以上の派遣会社に雇用されている方も、条件を満たせば加入が義務付けられます。
以下のすべての条件を満たす場合、健康保険への加入が必須となります。
- 所定労働時間が週20時間以上30時間未満
- 月収 8.8万円以上
- 2ヶ月以上の雇用見込みがある
- 学生ではない(休学・定時制・通信制の場合は対象)
自分が加入対象かどうかを確認するには、雇用契約書をチェックし、勤務条件を派遣会社に問い合わせてみましょう。
厚生年金保険
健康保険と同様に、所定労働時間が週20時間以上・月収8.8万円以上などの条件を満たせば加入できます。
この制度は、国民年金に上乗せして支給される仕組みで、老後の生活資金をより手厚く確保できるのが特徴です。
また、老齢年金だけでなく、障害や死亡時にも給付が受けられるため、もしものときの保障も充実しています。
保険料は、企業と労働者が折半で負担となり、2025年度の保険料率は**18.3%(収入に対する割合)が適用されています。
この保険料は将来の年金額に直接関係するため、加入期間や年金記録を定期的に確認することも大切です。
保険料の計算式(2025年度時点)
厚生年金保険料=標準報酬月額×18.3%(保険料率)
※保険料は事業主(会社)と本人(従業員)で半分ずつ(折半)負担します。
つまり、実際に従業員が負担するのは【保険料全体のうち9.15%】に相当します。
具体的な金額例(2025年度・月収ベース)
(標準報酬月額) |
(月額・本人負担) |
(月額・会社負担) |
(本人負担+会社負担) |
|---|---|---|---|
| 100,000円 | 9,150円 | 9,150円 | 18,300円 |
| 150,000円 | 13,725円 | 13,725円 | 27,450円 |
| 200,000円 | 18,300円 | 18,300円 | 36,600円 |
| 250,000円 | 22,875円 | 22,875円 | 45,750円 |
介護保険
介護保険は、40歳以上の方が対象で、健康保険に加入していれば自動的に適用されます。要介護や要支援に認定された場合、介護サービスを1〜3割の自己負担で利用できるのが特徴です。
保険料は健康保険料と合わせて徴収されるため、別途の支払い手続きは不要です。40歳を迎える前に制度の仕組みを理解しておくことで、将来の生活設計や万が一の備えにもつながります。不明点や気になることがあれば、派遣会社の担当者に事前に確認しておくと安心です。
雇用保険
雇用保険は、所定労働時間が週20時間以上あり、かつ31日以上の雇用見込みがある場合に加入できる制度です。
加入することで、失業時の給付金や育児休業中の支援金、スキルアップを目的とした給付金など、さまざまなサポートが受けられます。おもな給付内容は以下のとおりです。
| 失業手当 | 再就職までの生活を支える給付 退職理由や雇用保険の加入期間により支給日数が異なる |
| 育児休業給付金 | 育児休業を取得した際に支給 最初の6ヶ月は賃金の67%、以降は50%を支給 |
| 教育訓練給付金 | 厚生労働大臣が指定する講座を受講した場合に、費用の一部が支給される |
派遣社員が雇用保険に加入する際は、雇用主となる派遣会社が手続きを行います。また、自分が雇用保険に加入しているかどうかは、給与明細の控除欄を確認することで把握できます。
なお、雇用保険の給付を受ける際には、手当の種類ごとに条件が定められており、各要件を満たす必要があります。制度を利用したい場合は、ハローワークや派遣会社に事前に確認しておくと安心です。
労災保険
労災保険は、すべての労働者を対象とした制度で、業務中や通勤中に発生した事故やけがに備える制度です。保険料は事業者が全額負担するため、派遣社員本人の負担はありません。労災保険のおもな給付内容は、以下のとおりです。
| 療養補償給付 | 業務中のけがや病気の治療費を全額補償(自己負担なし) |
| 休業補償給付 | 労災により仕事を休んだ期間中、給料の約6割が支給される |
| 障害補償給付 | けがや病気によって障害が残った場合、障害等級に応じた一時金または年金が支給される |
| 遺族補償給付 | 業務災害で亡くなった場合、遺族に対して年金または一時金が支給される |
| 介護補償給付 | 重度の障害により介護が必要と認定された場合、介護費用の一部または全額が支給される |
労災保険の給付を受けるには、労災として認定されるための一定の条件を満たす必要があります。
万が一事故が発生した場合は、速やかに派遣元と派遣先企業の両方に状況を報告することが大切です。
派遣社員の社会保険料はどのくらい?

派遣社員が実際に支払う社会保険料の計算方法について詳しく紹介します。
保険料は派遣会社と労使折半で負担
社会保険料(健康保険・厚生年金・介護保険)は、派遣会社と派遣社員が半分ずつ負担する「労使折半」が基本となっています。たとえば健康保険料が10%の場合、派遣社員が実際に負担するのは半分の5%です。
また、雇用保険も派遣会社と派遣社員で費用分担されており、派遣社員の負担率は0.55%(一般事業の場合)と比較的低く設定されています。一方、労災保険は保険料の全額を派遣会社が負担するため、派遣社員の自己負担はありません。
保険料計算に使われる「標準報酬月額」
社会保険料(健康保険・厚生年金など)は、実際の給与額ではなく、「標準報酬月額」に基づいて計算されます。標準報酬月額とは、毎年4~6月の給与の平均額をもとに決定され、国が定める等級表に当てはめて算出される金額です。
たとえば、4〜6月の平均給与が20万円の場合、その金額が標準報酬月額として登録され、7月から翌年6月までの1年間は、その等級に応じた保険料が適用されます。なお、賞与に対しても「標準賞与額」が別途設定され、保険料が計算されます。
派遣社員が社会保険に加入するメリット

派遣社員が社会保険に加入する具体的なメリットについて詳しく紹介します。
老後に受け取れる年金額が増える
社会保険に加入すると、老後に受給できる年金額が、国民年金のみの場合に比べて大幅に増えます。
厚生年金に加入している場合、国民年金(老齢基礎年金)に加えて「老齢厚生年金」も支給されるため、老後の生活資金にゆとりが生まれやすくなります。
また、厚生年金に加入していると、障害を負った場合の「障害厚生年金」や、万が一の際に家族へ支給される「遺族厚生年金」などの保障も加わるため、将来に対する備えとしての安心感も高まります。
会社が保険料の半分を負担してくれる
社会保険では、派遣会社が保険料の一部または半分を負担する「労使折半」のしくみがとられています。そのため、派遣社員の自己負担額が軽減され、保険に加入しながらも手取りの減少を最小限に抑えることができます。
会社が負担している保険料は、見方を変えれば「実質的に給与の一部を補助してもらっている」とも言えるため、同じ収入であっても、生活の安定性や将来への備えという点で、大きな安心感につながります。
傷病手当金・出産手当金などの給付が受けられる
社会保険に加入していれば、病気やけが、出産などでやむを得ず仕事を休むことになった場合でも、一定の条件を満せば「傷病手当金」や「出産手当金」などの給付を受けとることができます。
手当金の給付によって休業中の収入減少を補い、生活費への不安を和らげることができます。とくに契約期間が決まっている派遣社員にとっては、働き方の安定性を高める制度といえるでしょう。
派遣社員が社会保険に加入する際の注意点

派遣社員が社会保険に加入する際に知っておくべき注意点について詳しく紹介します。
保険料の負担により手取り額が減る場合もある
社会保険に加入すると、健康保険・厚生年金・雇用保険などの保険料が給与から差し引かれるため、実際に受け取る手取り額が減ったように感じられることがあります。
これまで扶養の範囲内で就業していて、社会保険料の自己負担がなかった方にとっては、手取りの変化に戸惑うこともあるでしょう。保険料の負担によって、手取り金額が減るため、世帯全体の家計や生活に影響を与えることもあります。
社会保険に加入する前には、加入条件だけでなく、保険料負担額や手取り額への影響を事前にシミュレーションしておくことが重要です。
扶養から外れる可能性がある
社会保険に加入すると、配偶者の健康保険の被扶養者資格から外れる可能性があります。先述のとおり、週20時間以上働き、かつ月収が8.8万円(年収換算106万円相当)を超える場合など、一定の条件を満たすと、健康保険と厚生年金に加入が必須です。
扶養から外れると、配偶者が受けていた所得控除が適用されなくなったり、勤務先で支給されていた家族手当がなくなったりするケースもあります。そのため、事前に加入条件や内容を確認しておくことが大切です。
短期雇用では社会保険のメリットを活かしにくい場合がある
社会保険は短期間の雇用であっても加入が必要になる場合がありますが、加入期間が短いと、制度のメリットを十分に受けられないこともあるため注意が必要です。
たとえば、厚生年金は加入期間に応じて将来の年金額が決まるため、契約期間が短い場合は、年金の増加幅が限定的になる可能性があります。また、雇用保険についても、失業給付の支給には一定の加入期間が必要であり、加入期間が短いと受給資格を満たせなかったり、給付日数が少なくなったりすることがあります。
短期契約を繰り返す働き方を希望する場合でも、制度ごとの適用条件や給付要件を事前に確認しておくことが重要です。
派遣社員の退職・契約終了後の社会保険手続き

派遣社員の契約終了時に必要な社会保険手続きについて詳しく紹介します。
契約終了後に必要な手続き
派遣契約が終了すると、健康保険証の返却や社会保険資格の喪失手続きが必要になります。手続きは基本的に派遣会社が対応しますが、派遣社員本人も忘れずに対応状況を確認することが大切です。
社会保険の資格は契約満了と同時に失われるため、健康保険証は速やかに返却しましょう。また、離職票や雇用保険被保険者証が必要な場合は、派遣会社に発行を依頼する必要があります。
各種手続きが遅れると、次の就業先での社会保険加入や医療費の支払いに支障をきたすこともあります。そのため、契約終了日を事前に確認し、必要書類の準備や返却スケジュールを把握しておくと安心です。
次の就業まで空白期間がある場合の手続き
派遣契約満了後に次の仕事までの期間が空く場合は、健康保険と年金の切り替えが必要です。健康保険は任意継続か国民健康保険に加入し、年金は国民年金に切り替える必要があります。
手続きをしないと、医療費を全額自己負担することになりかねず、年金の未納期間が発生することもあるため、対応方法について理解しておきましょう。健康保険の任意継続と国民健康保険については下記で詳しく解説します。
任意継続被保険者制度を利用する方法
任意継続被保険者制度は、退職後も最長2年間、在職中の健康保険を継続できる制度です。退職の翌日から20日以内に申請が必要で、保険料は退職時の標準報酬月額をもとに決まります。
たとえば、標準報酬月額が24万円だった場合、協会けんぽ東京支部の月額保険料は約23,784円です。扶養家族がいる場合も追加料金は発生しないため、家族が多い場合には経済的なメリットがあるといえます。
なお、任意継続被保険者制度には加入条件があるため、切り替えを検討する場合は早めに派遣会社に相談しましょう。
国民健康保険へ切り替える方法
国民健康保険に切り替えるには、退職の翌日から14日以内に市区町村の役所で手続きを行います。保険料は前年の所得と世帯構成によって決まり、自治体ごとに異なります。
任意継続とは異なり、家族それぞれに保険料が発生します。家族の人数や収入状況によって負担額が大きく変わるため、事前に市区町村で保険料の試算を受けておくと安心です。
派遣社員の社会保険に関するよくある質問(FAQ)

社会保険について、よくある疑問や質問について詳しく紹介します。
社会保険に入りたくない場合はどうすればいい?
社会保険は、一定の条件を満たすことで加入が義務付けられる制度です。そのため、どうしても加入を避けたい場合は、加入条件にあてはまらない働き方を選ぶことは可能です。
ただし、条件に該当しなくても長期的に働く見込みがある場合などは、社会保険の代わりに国民健康保険や国民年金に個人で加入する必要があります。長期的な保障や負担額とのバランスをよく考えて選択することが大切です。
パソナでは、扶養範囲内のお仕事や、短時間勤務ができるお仕事など、豊富なお仕事を掲載しています。希望条件に合った働き方を選びたい方はぜひ、ご覧ください。
ダブルワーク時の社会保険はどうなる?
派遣社員がダブルワークをする場合、所属する派遣会社が同一か複数かによって社会保険の取り扱いが異なります。
1. 同一の派遣会社で複数の就業先に勤務する場合
同じ派遣会社から異なる就業先に派遣されている場合は、勤務時間や収入を合算して社会保険の加入判定が行われます。
合計で以下の条件を満たすと、加入対象となります。
・週20時間以上の勤務
・月収8.8万円以上(年収106万円相当)
・雇用見込みが2か月以上 など
2. 異なる派遣会社から就業する場合
就業先がそれぞれ異なる派遣会社からである場合は、派遣契約ごとに加入条件を満たすかどうかで判定されます。
この場合、複数の勤務を合算して条件を満たしても、社会保険に加入することはできません。それぞれの派遣会社で条件を個別に満たしている必要があります。
3. 複数の派遣会社で条件を満たす場合
複数の派遣契約でそれぞれが社会保険の加入条件を満たした場合は、「二以上事業所勤務届」の提出が必要です。
そのうえで、下記手続きが行われます。
・健康保険と厚生年金保険 → 主たる勤務先(※一般的には勤務時間や賃金の多い方)の派遣会社で加入
・雇用保険 → 賃金の高い勤務先の派遣会社でのみ加入
ダブルワークは働き方の幅が広がる一方で、社会保険の扱いが複雑になりやすいため、事前に各派遣会社へ勤務条件や加入可否を確認しておきましょう。
自分の加入状況を確認する方法は?
派遣社員が社会保険の加入状況を確認するには、「ねんきんネット」や「マイナポータル」といったオンラインサービスを利用するのがおすすめです。厚生年金の加入履歴や保険料の納付状況、将来の年金見込額などを確認できます。
健康保険の加入情報や医療費の履歴も把握できるため、定期的に確認しておくと安心です。契約の更新や切り替えが多い派遣社員は、手続き漏れがないかを自分でも確認しておきましょう。
保険料は派遣先と派遣元のどちらが負担?
社会保険料は、派遣会社(派遣元)が労使折半で負担し、派遣先企業が直接負担することはありません。派遣社員は派遣会社と雇用契約を結んでいるため、保険の加入や給付の手続きも派遣会社が行います。
そのため、社会保険に関する問い合わせは、派遣先ではなく派遣会社に相談することが基本です。
派遣社員は条件を満たせば社会保険へ加入できる

2024年10月の法改正により、社会保険の適用範囲が拡大され、従業員51人以上の派遣会社で一定の条件を満たす派遣社員も、健康保険や厚生年金に加入できるようになりました。
社会保険の加入は、医療費の自己負担軽減や年金の増額、労災時の保障など、多くのメリットがあります。
パソナでは、一定の就業条件を満たす派遣社員の方には社会保険にご加入いただいています。社会保険に関する相談窓口も設けていますので、制度についてご相談も可能です。
扶養内で働きたい方からフルタイムで働きたい方まで、ライフスタイルにあわせて選べる豊富なお仕事を掲載しています。ぜひチェックしてみてください。