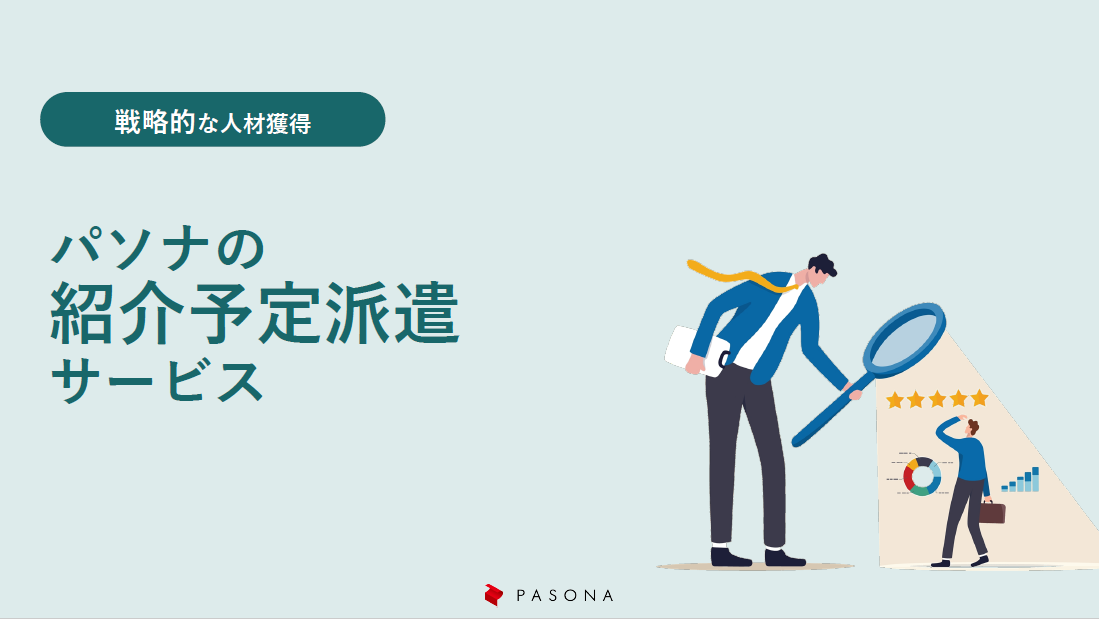おすすめ特集・コラム【人事担当者必見】派遣法の3年ルールとは?概要や例外、期間延長の方法を解説!

更新日:2025.10.28
- 人材派遣

長期での派遣利用を導入・検討している企業にとって、派遣法の「3年ルール」は重要な規則です。必要な対応を取らずに3年を超えて派遣社員を受け入れると、違法派遣として罰則を受ける可能性があります。
本記事では3年ルールの概要と3年を超えて派遣社員を受け入れる方法について解説します。長期の派遣利用を検討している方はぜひ参考にしてください。
【人手不足でお困りの担当者へ】
>>即日就業可能なスタッフ多数登録!パソナの人材派遣サービスはこちら
需要の高い人材が見えてくる!派遣市場・派遣動向レポート
地方8エリア(全国・北海道・東北・北関東・北信越・中国・四国・九州)の派遣市場・派遣動向をまとめました。
- 稼働者動向(職種・業種・職種別平均年齢)
- 受注企業動向(職種・業種)
人材派遣サービスを活用される際にぜひお役立てください。
派遣法の3年ルールとは?
労働者派遣法では、派遣労働者の安定した雇用と適切な労働環境の確保を目的として、派遣労働者の受け入れ期間を最長3年と定めています。以前は業種により派遣受け入れ期間の上限が異なりましたが、2015年の法改正で業種問わず3年に統一されました。
非正規雇用では、「5年ルール」も存在します。5年ルールとは、有期雇用契約の契約期間が5年を超えた場合、労働者からの申込みで無期雇用契約に転換できる制度です。派遣社員に限らず、契約社員、パート、アルバイトなど、有期雇用契約で働く全ての人が対象となります。5年ルールは雇用契約に関するルールであるため、派遣の受け入れ期間を定めた3年ルールとは区別されます。
違反した場合どうなる?
3年ルールに違反すると、行政指導や罰則の対象となったり、「労働契約申込みみなし制度」が適用される場合があります。
労働契約申込みみなし制度とは、違法派遣の状態を派遣先が知りながら派遣労働者を受け入れている場合、派遣先が派遣労働者に対して、派遣元と同条件の労働契約を申込みをしたものとみなす制度です。この制度が適用された場合、派遣労働者が承諾すれば、派遣先企業での直接雇用が成立することになります。
パソナの紹介予定派遣サービス
派遣期間中に企業・スタッフ双方が適正を判断出来ることで、直接雇用後に安定就業・長期就業につながりやすくなります。ミスマッチや離職を予防して人材活用につなげます。
3年ルールには2種類の期限がある
派遣法の3年ルールには、事業所単位と個人単位の2つの期限があります。いずれも期限満了日を「抵触日」と呼びます。ここでは2つの期限の考え方について解説します。
派遣先の「事業所単位」の期間制限
事業所とは、①工場、店舗、事務所など場所的に独立しており、②人事、経理、指導監督、働き方がある程度独立していて、③施設として一定期間継続するものを指します。基本的には雇用保険の適用事業所単位と同様となります。
同一の事業所内では、部や課に関係なく、派遣の受け入れ期間を最大3年としています。起算日は当該事業所で最初に派遣を受け入れた日ですので、途中で派遣社員の交代や別部署での新規受け入れがあっても、受け入れ期間はリセットされません。
参考:労働者派遣法のルール「事業所単位の派遣期間制限」とは?
派遣労働者の「個人単位」の期間制限
個人単位の期間制限では、同一組織における3年以上の就業が禁止されています。組織とは、①業務としての類似性、関連性があり、②組織の長が業務配分、労務管理上の指揮監督権限を持つ単位のことです。
例えば人事部部長が部内の指揮監督権限を持っている場合、派遣社員の受け入れ先が給与計算課から労務課に変わっても、両者は同一組織であるとみなされます。そのため、両方の課を合わせて最長3年までしか受け入れることができません。
参考:労働者派遣法のルール「個人単位の派遣期間制限」「事業所単位の派遣期間制限」とは?
労働者派遣法を正しく理解して派遣サービスを活用!人材派遣ガイドブック
労働者派遣法は、労働者の保護や労働市場の健全な運営を目的とした法律です。人材派遣に関する知識を正しく理解し、適切な人材配置につなげるための参考資料としてご活用ください。
3年ルールの例外
派遣法の3年ルールは全業種に適用されますが、派遣社員の属性やプロジェクトにより3年ルールが適用されないことがあります。派遣法第40条の2に記載されている3年ルールの例外についてみてみましょう。
60歳以上の派遣社員
最初の例外は、派遣期間の満了時に60歳を超えている派遣社員です。60歳以上の派遣社員は、「雇用の機会の確保が特に困難である派遣労働者であってその雇用の継続等を図る必要があると認められるもの」に該当します。
派遣元企業に無期雇用されている派遣社員
派遣元で無期雇用契約を結んでいる派遣社員には、3年ルールが適用されません。無期雇用労働者であるため、派遣先企業の都合で派遣契約が突然終了したとしても、派遣元企業での雇用が保障されているからです。
有期プロジェクト業務
有期プロジェクトに従事する場合は、3年ルールの適用外となります。ただし対象となるプロジェクトは、契約時に3年以内に完了が見込まれており、「事業の開始、転換、拡大、縮小又は廃止のための業務」のみです。こうしたプロジェクトの派遣契約は終了時期が明確で、むやみに契約期間が延長される可能性が低いためです。
日数限定業務
日数限定業務に従事する場合は3年ルールの適用外です。日数限定業務とは、月の所定労働日数が派遣先企業の通常労働者の半数以下であり、かつ10日以下の日数で発生する業務のことです。例えば、月に1日の棚卸し業務や、土日のみ開催される住宅展示場の案内業務などです。
なお、月の所定労働日数が10日以下でも、繁忙期の増員などのように月に10日を超えて発生している業務は3年ルールが適用されますので、注意が必要です。
産前産後、育児休業・介護休業代替業務
派遣先企業の社員が、産前産後休業、育児休業、介護休業を取得する場合の、代替の業務は3年ルールの適用外となります。これらの休業は、取得期間がある程度決まっています。そのため、こうした代替業務は社員の復職とともに派遣契約の終了が見込まれ、有期プロジェクト業務と同様に、事業所での派遣の受け入れ期間が3年を超えたとしても、派遣契約の継続が可能です。
3年を超えて派遣社員を受け入れたいとき
3年ルールは全業種に適用されますが、適切な対応をすることで、3年ルールが適用される派遣社員も3年を超えて受け入れることができます。その方法について以下で解説します。
事業所単位の期間延長手続き
同一の事業所内で3年を超えて派遣社員を受け入れたいときは、該当する派遣可能期間満了日の1ヶ月前までに、事業所の過半数労働組合等からの意見聴取をおこないます。
意見聴取の際は、過半数労働組合等に対して対象事業所や延長しようとする期間を書面で通知します。合わせて、派遣先の派遣労働者数や無期雇用労働者数の推移といった統計情報も提供することが望ましいとされています。
書面内容に対して過半数労働組合等から異議が上がった場合は、延長前の派遣可能期間が終了する前日までに、派遣可能期間の延長理由や、当該異議への対応方針を説明します。
個人単位の対処法

同一の派遣社員に3年を超えて業務を依頼したい場合は、3つの方法があります。
派遣契約を継続したい場合に派遣元企業に当該社員の無期雇用転換を依頼し、常用型派遣として受け入れます。
一般派遣のまま派遣契約を継続する場合は、受け入れ組織を変更することで派遣期間が延長できます。例えば、総務部で3年間受け入れた後、同じ派遣社員を営業部で受け入れます。派遣契約を継続する場合は、事業所単位の抵触日に注意しましょう。
最後に自社で直接雇用に切り替える方法です。この場合、派遣就業時よりも雇用条件が悪くならないように留意しましょう。
クーリング期間について
クーリング期間とは、派遣可能期間の抵触日をリセットする期間です。3ヶ月以上、派遣社員を受け入れない期間があれば、再度同じ事業所で同一の業務について派遣社員を3年間受け入れられるようになります。
クーリング期間の設定は派遣社員の受け入れを再開できる一方、リスクも伴います。派遣社員にとっては3ヶ月の離職期間が発生する可能性があります。派遣先企業にとっても、クーリング期間中は正社員の負担が一時的に増える可能性があります。また派遣先企業は派遣社員の指名ができないため、クーリング期間後に適切な派遣社員が見つかる保証がないこともリスクになります。
関連記事:派遣の抵触日以降はどうなる?リセットまでのクーリング期間を解説
3年ルールのメリット・デメリット
最後に派遣の3年ルールのメリットとデメリットについて解説します。
3年ルールのメリット
1つ目のメリットは、属人化リスクの解消です。長くても3年で担当者が変わるため、特定の社員に対する過度な依存や、業務のブラックボックス化を防止できます。
2つ目は、即戦力を直接雇用できる可能性があることです。3年の派遣期間終了後に直接雇用に転換することで、自社で既に活躍している派遣社員を即戦力として採用することができます。このことは、採用コストの低減やミスマッチのリスクを下げる効果があります。
3年ルールのデメリット
3年ルールのデメリットの1つ目は、教育コストがかかることです。最長3年ごとに新たな派遣社員を契約するため、後任の検討や、引き継ぎ、教育コストが発生してしまいます。
2つ目は、帰属意識の低下です。派遣社員は長くても3年で派遣先が変わることを理解しているため、派遣先企業への帰属意識を持ちにくくなります。コンプライアンス等の研修や定期面談の実施、チームのコミュニケーション活性化といった、派遣社員の帰属意識やモチベーションを高める工夫が必要です。
労働者派遣法のルールを解説!
人材派遣のご利用にあたって労働派遣法について解説しています。
”派遣期間制限とは?”、”派遣を活用する上での注意ポイントは?”、”派遣禁止業務って何?”など1つ1つご確認いただけます!
まとめ:3年ルールを理解して長期派遣を活用しよう
本記事では長期派遣で重要となる3年ルールについて解説しました。3年ルールの目的や対応方法を正しく理解し、適切に派遣を活用しましょう。
派遣社員には、いわゆる正社員である無期雇用労働者とは異なる法律が適用されます。パソナでは様々な業種・職種の派遣実績があり、派遣労働者の待遇確保や雇用安定措置の対応方法に関する事例が蓄積されています。派遣の利用やコンプライアンス上の留意点を詳しく知りたい方はぜひご相談ください。
派遣の手引き
人材派遣サービスをご利用いただく上での、 コンプライアンス上の留意点等をわかりやすくQ&A方式で解説しております。 。 巻末の「『労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準』に関する 疑義応答集」等も、あわせてご参照ください。
即日就業可能なスタッフ多数登録!パソナの人材派遣サービス
パソナの人材派遣サービスでは営業と人選担当が密に連携し、適切なマッチングとスピーディーな人選、ご紹介を可能に。充実した教育・研修制度と高いスタッフ満足度で安定就業を実現できる体制を実現しています。