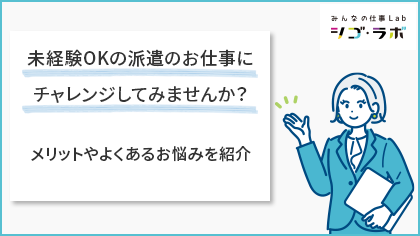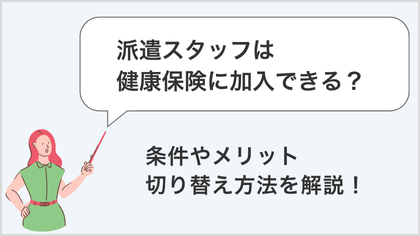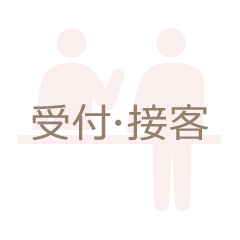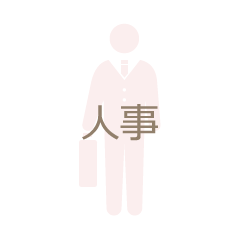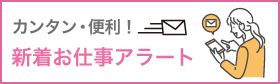扶養内で働けるのはいくらまで?
「年収の壁」や扶養内で働くメリット・注意点を解説
更新日:2025年10月21日
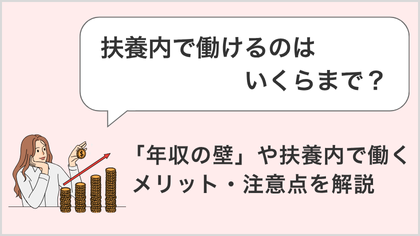
「扶養内で働きたい」と考えている方にとって、基本を理解しておきたいのが「年収の壁」です。
「よく話題になるけれど、仕組みがよくわからない…」と感じている方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、年収の壁についてわかりやすく解説しながら、扶養内で働くメリットや注意点についてもご紹介します。
「扶養内で働く」とは?

「扶養内で働く」とは、主に家計を支えている人(配偶者や親など)の扶養家族として、一定の収入の範囲内で働くことです。扶養には「税法上の扶養」と「社会保険上の扶養」の2つの種類があり、扶養に該当すると、税金や社会保険料の負担を軽減することができます。
それぞれ仕組みが異なるため、詳しく見ていきましょう。
税法上の扶養
「税法上の扶養」とは、所得税や住民税を計算するときに、扶養している人が扶養控除や配偶者控除といった税金の控除を受けるための仕組みです。
扶養控除とは、扶養している親族がいる場合に、一定の金額を所得から差し引くことができる制度を指します。一方、配偶者控除は、所得税法上の控除対象配偶者がいる場合に適用される制度です。
扶養控除や配偶者控除を受けることで、扶養している人(納税者)の税負担を軽減することができます。
社会保険上の扶養
「社会保険上の扶養」とは、健康保険や年金の制度において、扶養している家族が自身の保険に加入できる仕組みです。
扶養される人は自分で保険料を負担することなく、医療費の自己負担が原則3割になったり、国民年金保険料を自分で納めなくてもよい「第3号被保険者」として扱われたりします。
年収の壁の種類と違い

扶養内で働く場合、多くの方が意識するのが「年収の壁」です。年収の壁とは、収入がある金額を超えたとき、税金や社会保険の負担が変わるラインを指します。
税金に関わる壁と社会保険に関わる壁があり、それぞれ設定されている年収額が異なります。
税金に関わる壁となる年収額には、100万円・103万円・150万円・201万円、社会保険に関わる壁となる年収額には、106万円・130万円の壁があります。どの壁を基準にするかは、税負担と社会保険料の負担のどちらを優先するかなど、目的によって考え方はさまざまです。
税金に関わる壁、社会保険に関わる壁、それぞれの年収ラインがどのような内容の基準になっているのか、詳しくみていきましょう。
- 2025年10月21日時点の内容です。
税金に関わる壁
年収100万円の壁
「住民税」に関わる基準です。多くの自治体では、年収100万円以下であれば住民税が非課税になり、100万円を超えると住民税がかかり始めます。この金額基準は、自治体によって異なることがあるため、確認しておくと安心です。
年収103万円の壁
「所得税」に関わる基準で、扶養する人が「配偶者控除」を受けられるかどうかの分かれ目となるラインです。扶養される人の年収が103万円以下なら、扶養する人の所得から38万円が控除され、税負担が軽くなります。
103万円を超えた場合は、「配偶者控除」ではなく「配偶者特別控除」に切り替わります。配偶者特別控除は、配偶者の所得金額に応じて控除額が細かく設定されているため、下記より確認してみてください。
年収150万円の壁
「配偶者特別控除」が最大限に受けられる年収額です。扶養される人の年収が150万円以下であれば、扶養する人は最大38万円の控除(配偶者控除と同額)を受けられます。
150万円を超えると、段階的に控除額が少なくなります。
年収201万円の壁
「配偶者特別控除」の適用が完全になくなるラインです。扶養される人の年収が201万円を超えると、扶養する人は配偶者に関する控除を一切受けられなくなります。
社会保険に関わる壁
年収106万円の壁
社会保険(健康保険・厚生年金)に自分で加入し、給与から健康保険料や厚生年金保険料が天引きされるようになるかどうかの基準となるラインです。
従業員数が51人以上の企業に勤務していて、かつ次の条件をすべて満たす場合に、年収106万円以上になると扶養の枠から外れ、自分で社会保険に加入する義務が発生します。
・週の所定労働時間が20時間以上
・賃金の月額が8.8万円以上(年収計算で約106万円)
・継続して2カ月を超えて働く見込み
・学生ではない(夜間の学生などは対象になる場合あり)
年収130万円の壁
社会保険の扶養に入れるかどうかの一般的な基準となる年収額です。扶養に入る人の年収が130万円未満であれば、扶養する人の社会保険の「扶養家族」として扱われます。自分で保険料を負担することなく、扶養の枠内で社会保険を利用できます。
年収130万円以上になると、自分で社会保険に加入し、保険料を支払う必要があります。
- 年収130万円未満が目安ですが、実際には収入の見込みや勤務先の健康保険組合の判断によって取り扱いが異なる場合があります。
年収の壁について詳しくは、厚生労働省の下記の資料もご参考ください。
扶養内で働く3つのメリット

扶養内で働くことは、実生活においてどのようなメリットがあるのでしょうか。
1.社会保険料の負担が少なくなる
健康保険や年金は、通常は自分が働いた分の給料から保険料が差し引かれますが、扶養内で働くことで扶養する人の社会保険に加入できるため、自分で保険料を負担する必要がありません。
2.配偶者の税負担が軽くなる
扶養内で働くと、「配偶者控除」や「配偶者特別控除」を受けられるようになります。配偶者が納める税負担が軽くなり、世帯全体の手取り額が増えるのがメリットといえます。
3.ライフスタイルに合わせて働ける
扶養内で働くことの魅力は、税金や社会保険料の面だけではありません。自分や家族のライフスタイルに合わせて働き方を選びやすい、という点も大きなポイントです。
「短時間勤務」や「シフト勤務」を条件として選ぶケースも多いため、子育てや介護などと両立しながら無理なく働くことができます。
扶養内で働くうえでの注意点

扶養内で働く場合、知っておくべき注意点もあります。
次の4つのポイントを押さえておきましょう。
1.勤務先から、扶養内で働くことへの理解を得る
扶養内で働く場合、「1年間の収入合計」が基準となります。例えば、シフト勤務で働く場合など、「繁忙期だから」と多めにシフトを入れてしまう月があると、基準を超えてしまう可能性があります。
また、月々の給与額はもちろん、「臨時手当」「ボーナス」などの支給も考慮する必要があります。
予想外の収入を見落とさないためには、「扶養内で働きたい」という希望を勤務先に伝え、シフト調整や収入見込みについて理解を得ることが大切です。合わせて、年間の見込み収入を定期的に確認し、しっかりと調整・管理していくのもポイントです。
2.給与が「交通費込み」かどうかを確認する
扶養内で働くうえで見落としやすいのが、交通費の扱いです。給与が「交通費込み」である場合、税金上は月15万円までの通勤手当は非課税ですが、社会保険上は、交通費も収入に含まれるため注意が必要です。
例えば、月の支給額が「給与10万円+交通費1万円」である場合、社会保険上は「11万円」として計算されます。給与である10万円を基準に調整をしていると、年収の基準額を超えてしまうため気を付けましょう。
3.「傷病手当」「出産手当」の対象外となる
扶養内に入っていれば保険証は利用できますが、自分が被保険者(社会保険に加入している本人)ではないため、次の手当を受け取ることができません。
・傷病手当金(病気やケガで働けなくなったときの生活保障)
・出産手当金(出産で休業する期間の所得保障)
これらは健康保険の被保険者のみに支給される制度なので、覚えておきましょう。
4.企業が独自に設けている規定がないか確認する
税務上の扶養や社会保険上の扶養には全国共通の基準がありますが、企業によっては独自に規定を設けているケースがあります。例えば、「配偶者手当」や「家族手当」などです。
これらは法律で決められたものではなく、企業が独自に設ける福利厚生制度となります。そのため、企業の規定によっては、配偶者の年収が一定の金額を超えると、こうした手当が支給されなくなる場合があります。
税金や社会保険だけでなく、扶養する人の所属企業の制度も合わせて確認すると、調整を図りやすくなるでしょう。
扶養内でよくある質問(FAQ)
扶養内で働けるのはいくらまで?
税法上の扶養では、所得税に関わる基準である年収103万円までが目安となり、月あたりに換算すると約8万5,800円です。
一方、社会保険上の扶養では年収130万円までが適用のラインとなり、月あたり約10万8,300円が目安になります。
扶養内で働く場合、年末調整は必要?
年収103万円以下で所得税がかからない場合でも、「扶養控除等申告書」を勤務先に提出していれば、年末調整が必要です。派遣、パート、アルバイトなどの雇用形態に関わらず、忘れずに対応しましょう。
扶養内で働く場合、確定申告は必要?
確定申告が必要かどうかは、所得税が発生するかどうかによって判断されます。そのため、年収103万円を超える場合に、原則として確定申告が必要となります。
派遣で扶養内のお仕事を探そう!

「扶養内で働きたい」と考えている方は、派遣でお仕事を探してみませんか?
派遣では、派遣会社の多くがお仕事探しから就業中までのサポート体制を整えています。働き方のご希望や、就業中のお悩みなど、気軽に相談することができるので安心です。
パソナでは、お仕事のことはもちろん、ご家庭のことや健康のことなどについても相談できるライフサポートサービスが充実しています。
まずは、「扶養範囲内」の条件で自分に合うお仕事を探してみてください。