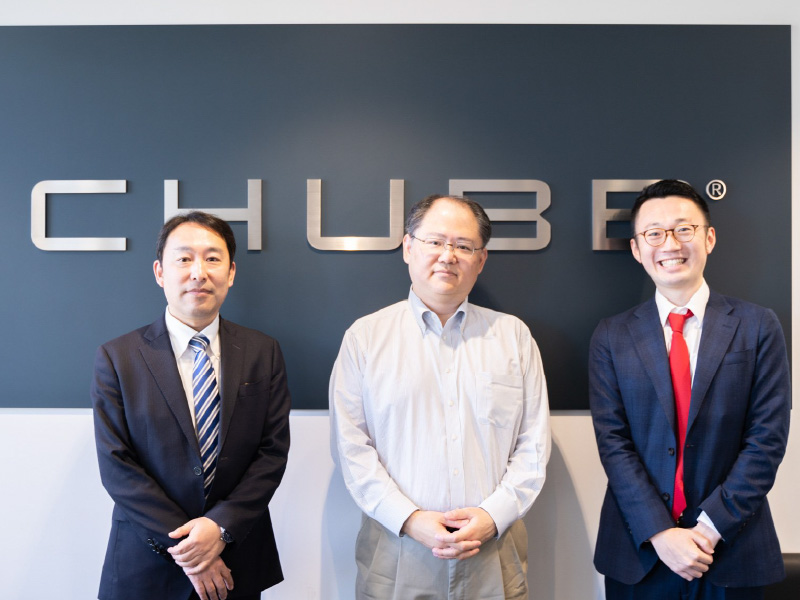おすすめ特集・コラム業務委託とは?請負と委任・準委任の違いや契約時の注意点を詳しく解説

更新日:2025.07.10
- 人材派遣
- BPO・アウトソーシング

自社の業務を外部に委託する「業務委託」。人材不足解消の一手として多くの企業が取り入れているサービスですが、契約の種類や法律上のルールなど、細かい部分まで正しく理解できている方は少ないかもしれません。
この記事では「業務委託」を取り上げ、請負と委任・準委任の違いや企業が活用するメリット、契約を結ぶ際の注意点について詳しく解説します。
【業務改善についてお困りの担当者へ】
>>導入実績800件以上!パソナのBPO・アウトソーシングサービスはこちら
BPOを安定的に運用する
パソナのノウハウ
BPOを安定的に運用するためのポイントをステップごとにお伝えします。BPOを運用していくうえで発生する課題と、それに対するパソナのソリューションを導入事例からご紹介しています。
業務委託とは
業務委託とは、外部の企業や個人に自社の業務を任せることをいいます。発注者から受けた仕事の完成または役務の提供に対して報酬が支払われる形式で、業務委託で働く人は労働法による制約を受けずに「事業主」として仕事を遂行します。
業務委託をおこなう際には仕事を依頼する側(発注者・委託者)と依頼を受ける側(受託者)との間で業務委託契約を結びます。あらかじめ業務内容や業務委託料、禁止事項などが契約で定められますが、発注者と受託者との間に指揮命令関係はなく、仕事の進め方について発注者が具体的な指示を出すことはできません。
なお、法律上「業務委託契約」という名称の契約はなく、民法上の「請負」「委任」「準委任」の契約を総称して「業務委託契約」と呼ぶのが一般的です。
関連記事:理解してますか? BPOと派遣の違い、BPOのメリット・デメリット、BPO企業の選定ポイント!
業務委託契約と請負契約の違い
先述したように、業務委託契約は「請負契約」「委任契約」「準委任契約」を総称したものとして使われており、請負契約は業務委託契約の一種と考えることができます。ただし、業務委託契約のほうが請負契約よりも広い意味を持つ契約形態であり、両者は「仕事の完成が必須かどうか」という点で違いがあります。
請負契約は仕事の完成を必須とし、成果物に対して報酬が支払われます。言い換えれば、業務を遂行していても、任された仕事が完成しなければ報酬は支払われないということです。一方、業務委託契約は「請負契約」「委任契約」「準委任契約」の総称であり、何を目的とするかは契約によって異なります。請負契約であれば仕事の完成を目的としますが、委任契約・準委任契約においては業務の遂行を目的とし、仕事の完成がなくとも適正に業務がおこなわれていれば報酬が支払われます。
請負契約・委任契約・準委任契約の違い
請負契約・委任契約・準委任契約の違いを下表にまとめました。

各契約の特徴についてそれぞれ詳しく解説します。
請負契約
請負契約の内容は民法第632条にて以下のように規定されています。

請負契約は「仕事の完成」を委託する契約であり、仕事の結果(成果物の納品など)に対して報酬を支払います。請負契約では契約不適合責任が問われ、契約内容に適合しない目的物が引き渡された場合には受託者に対して目的物の修補や報酬の減額、損害賠償、契約解除の請求をおこなうことができます。
請負契約が交わされる業務の具体例としては、住宅の建設工事や運送業務、Webコンテンツ制作などが挙げられます。当事者間の意思の合致があれば契約成立となりますが、トラブルを避けるために契約書を交わすのが一般的です。
委任契約
委任契約の内容は民法第643条にて以下のように規定されています。

委任契約は「法律行為」を委託する契約であり、役務の提供に対して報酬を支払います。弁護士への訴訟行為の依頼や、税理士への確定申告手続きの依頼などが法律行為にあたります。
委任契約では業務の遂行が目的となり、成果物の完成責任は問われません。ただし、受任者の注意義務として「委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う」ことが規定されています(民法第644条)。善管注意義務をもって適正に業務が遂行されていれば、仕事の完成にかかわらず報酬が発生することになります。
準委任契約
準委任契約は「法律行為以外の業務」を委託する契約であり、役務の提供に対して報酬を支払います。準委任契約については民法第656条にて「法律行為でない事務の委託」との記載があり、委任契約の規定は準委任契約においても準用されます。
準委任契約が交わされる業務の具体例として、医師による診察やシステム開発、コンサルティングサービスなどが挙げられます。
業務委託契約と労働者派遣契約の違い
業務委託契約と労働者派遣契約の大きな違いは「指揮命令権がどこにあるか」という点です。
業務委託では受託者が自己の裁量と責任において業務を遂行します。従事者に対する指揮命令は雇用契約を結んでいる受託者が担い、発注者が従事者に対して具体的な業務指示をおこなうことはできません。一方、人材派遣では派遣会社と契約を結んでいる派遣先企業が派遣社員に対して直接業務指示をおこなうことができます。
従事者と発注者、派遣社員と派遣先企業との間に雇用関係が存在しない点は共通しますが、雇用関係になくても企業(=派遣先)が指揮命令をおこなうことができる人材派遣、雇用関係になく企業(=発注者)も業務指示を出すことができない業務委託という違いがあります。
関連記事:アウトソーシングと派遣の違い メリット・デメリットと活用のポイント
業務委託契約書に記載する主な事項
業務委託契約書に記載する主な事項を以下にまとめました。
関連記事:業務のアウトソーシングとは?メリット・デメリットや自社に適した種類、業務、導入の注意点を解説
業務内容
受託者がおこなう業務の内容、業務の提供方法、成果物の仕様などを明記します。
これらに加え、成果物の納品が発生する場合には納品方法や検収期間、検収結果の通知、修正回数の上限なども定めておく必要があります。
業務委託料
委託先に支払う報酬に関する情報を明記します。
具体的には、報酬の金額や計算方法、支払い時期(支払い期限)、支払い方法などを記載します。システム開発など長期に及ぶ案件の場合は着手金の有無や支払いサイクル(分割払いか一括払いか)などの情報も必要です。加えて、業務の遂行にあたって発生する諸経費の負担についても、あらかじめ契約書に明記しておくのが望ましいでしょう。
契約期間
契約期間や更新・解約に関する情報を明記します。
具体的には、契約の始期と終期、契約が長期に及ぶ場合は自動更新の有無、解約の手続きなどを記載します。また、契約期間満了後も存続する規定がある場合にはその旨を契約書に定めておく必要があります。
成果物の帰属
成果物の知的財産権が発注者と受託者のどちらに帰属するかを明記します。業務委託契約においては、成果物の引き渡しと同時に知的財産権も譲渡するのが一般的です。
なお、著作権の譲渡ついては「すべての著作権を譲渡する」という表現だけでは足りない点に注意が必要です。著作権法の規定により、翻訳権・翻案権(同法27条)および二次的著作物の利用に関する権利(同法28条)を委託者に譲渡する場合には「すべての著作権(著作権法27条および28条に定める権利を含む)を譲渡する」というようにその旨を明確に記載する必要があります。
再委託の可否
受託者による再委託を認めるかどうかについて明記します。
再委託とは、発注者から委託された業務をさらに別の事業者に委託することをいいます。業務委託契約書には再委託の可否とともに、再委託を認める場合に満たすべき条件を規定します。また、再委託がおこなわれると責任の所在があいまいになりやすいため、再委託によって損害が生じた場合は受託者が発注者に対して賠償する旨を記載しておくとよいでしょう。
禁止事項
委託業務の遂行にあたり、受託者に対して禁止したい事項がある場合はその詳細を明記します。ただし、業務委託の受託者を自社の社内規定で縛ることはできず、後述する「偽装請負」に該当しないよう注意が必要です。
その他の一般条項
契約の種類を問わず、どのような契約においても規定される標準的な条項を「一般条項」といいます。以下のような一般条項についても必要に応じて規定しておきましょう。
《一般条項の一例》

BPOの導入方法 ~業務委託をはじめるためのガイドBook~
業務効率UPやコスト削減などの導入効果が期待できるBPO。 限られた経営資源を有効に活用することが可能です。しかし導入時には課題も。課題とBPO導入の流れやポイントを解説します。
企業が業務委託を活用するメリット
企業が業務委託を活用するメリットとして以下の点が挙げられます。
自社のコア業務に注力できる
業務委託に適している業務として、すでに作業方法や手順がルール化されている定型業務が挙げられます。こうした業務は繰り返し発生するものの、手順書やマニュアルにしたがって作業を進めれば誰でも一定の品質を確保できるため、社外の人材にも任せやすい業務といえます。
定型業務を外部に委託することで、自社の従業員は重要な意思決定を伴うコア業務に注力できるようになります。コア業務は企業の利益に直結するため、基本的には自社の従業員が担うべき業務です。社外の人材でも問題なく業務を遂行できるものは委託し、重要度の高いコア業務に自社のリソースを集中投下することをおすすめします。
採用・育成コストを抑えられる
業務委託で働く人は、特定の業務の遂行に必要な知識やスキルを持っています。企業は即戦力となる人材に依頼できるため、新たな人材を採用して一から育てる必要がなく、採用・育成にかかるコストを抑えることができます。その分、自社の業務を滞りなく遂行できる人材の選定が不可欠となります。
加えて、業務委託においては仕事の完成や役務の提供に対して報酬が発生するため、当然ながら仕事がおこなわれなければ企業側にコストがかかりません。さらに、業務委託の人材は「事業主」として働いており、企業が社会保険料を負担することもありません。これにより、企業が「労働者」を雇用する場合と比べ、人材確保のコストも大幅に抑えることができます。
外部人材のノウハウを活用できる
業務委託を活用することで、自社にはないノウハウを取り入れられるメリットもあります。自社だけでは対応できない業務がある場合、外部人材が持つ専門的な知識やスキルを活用すれば自社で教育する時間や労力がかからず、すぐに業務に取り掛かることができます。
また、特定の業務に特化したプロ人材に任せることで、より完成度の高い成果物をつくり出すことができます。仕事の品質が上がれば顧客満足度が高まり、企業のイメージアップや業績向上につながることも期待できるでしょう。
【BPO導入・成功事例インタビュー】
保険のバックオフィス事務業務を一手に担う「中央業務センター」の改革に着手!BPO・アウトソーシング先の切り替えで、業務改善・品質向上に加え、従業員の残業時間削減にも成功された事例をご紹介します。
企業が業務委託を活用するデメリット
業務委託では外部人材が有する専門的な知見やノウハウを活用できます。企業にとってさまざまなメリットがある一方、業務委託を利用すると以下のようなデメリットが生じる可能性があることにも注意が必要です。
関連記事:経理業務アウトソーシングのメリット・デメリットは?後悔しない選び方と成功事例をご紹介
自社にノウハウが残りにくい
業務委託は社外の知見を活用できる一方で、自社にノウハウが残りにくいというデメリットがあります。業務委託の受託者は外部の人間であり、企業側が仕事の進め方や時間配分、人員配置などについて口を出すことはできません。自社が直接雇用し業務指示をおこなう正社員や自社の指揮命令下にある派遣社員などに仕事を任せる場合と比べ、外部の業務委託を活用することでノウハウが蓄積しにくい状態をつくってしまう可能性があります。
業務委託のノウハウを社内に残したい場合には、定期的な進捗報告やミーティングの機会を設けて情報共有を図ることが大切です。相手に任せきりにするのではなく、相互に協力しながら取り組むことを意識するとよいでしょう。
委託先の管理に手間がかかる
企業が業務委託を活用する場合、信頼できる委託先の選定から契約条件の決定、契約、発注、検収、支払いまでの一連の流れが必要です。複数の委託先があればそれぞれ個別に対応するため、委託先の管理に時間と手間がかかる点もデメリットとなるでしょう。
加えて、業務委託の発注者は指揮命令権を持たず、仕事の進め方に対して具体的な指示を出すことができません。業務委託は受託者の経験やスキル、モチベーションによって仕事の品質が左右されやすいため、企業側としては提出された仕事の品質管理の面で苦労するケースもあるでしょう。
BPO安定運用のための伴走型支援
BPOを安定的に運用するためのポイントをステップごとにお伝えします。またBPOを運用していくうえで発生する課題と、それに対するパソナのソリューションも導入事例からご紹介します。
業務委託契約の締結で注意すべきポイント
業務委託を利用する場合には発注者と受託者との間で業務委託契約を交わします。ここでは業務委託契約を締結する際に注意すべきポイントをご紹介します。
契約類型を明確にする
業務委託契約を締結する際は、業務委託の契約類型を明確にしておきましょう。契約書のタイトルは単に「業務委託契約書」と記載されることもありますが、業務委託契約には「請負契約」「委任契約」「準委任契約」の3つの類型が存在します。仕事の完成を目的とする請負契約のほか、業務の遂行を目的とし完成責任を問わない委任契約・準委任契約があり、契約の種類によって法律のルールが変わるため、民法上の請負・委任・準委任のどの契約に該当するかあらかじめ確認しておくことが重要です。
情報漏洩対策を徹底する
業務委託では自社が有する情報を外部の企業や個人と共有します。企業としては情報管理を徹底し、情報漏洩を未然に防ぐための対策が欠かせません。
具体的には、個人情報の取り扱いに関する規定や安全管理義務の体制整備、トラブル発生時の相談先などをあらかじめ確認し、信頼度の高い委託先を選定する必要があります。過去に情報漏洩を起こしたことがあるか、その場合にはどのような再発防止策を講じているかについても確認しておきます。また、業務委託契約書に秘密保持義務や再委託禁止の事項を規定する、業務委託契約とは別に秘密保持契約(NDA)を結ぶなど、適切な内容で契約を締結することも重要です。
委託元の指揮命令は違法となる
業務委託契約では受託者が自己の裁量で業務を遂行し、雇用関係にある従事者に指揮命令をおこないます。自社の業務を委託する発注者は、受託者や従事者に対して指揮命令をおこなうことができません。企業が業務委託を利用する場合には、仕事の進め方や時間配分といった業務上の指示を出せず、受託側に一任しなければならないことを理解しておく必要があります。
仮に委託元から指揮命令があった場合には「偽装請負」とみなされ、罰則の対象となる可能性があります。実際に業務委託を導入する際には、業務内容や検収基準を契約書に明記する、業務委託メンバーの座席を分けるなど、偽装請負の状態を避けるための対策が必要となるでしょう。企業が注意すべき偽装請負については次項で詳しく解説します。
業務委託で問題になりやすい「偽装請負」
業務委託の導入は、柔軟な人材活用における選択肢を増やすことになりますが、一方で「偽装請負」のリスクに十分な注意が必要です。
ここでは偽装請負の概要と企業ができる対策をご紹介します。
偽装請負とは
偽装請負とは、形式的には業務委託(請負・委任・準委任)でありながら、実態としては労働者派遣になっている状態をいいます。
業務委託の場合、発注者と受託者・従事者との間に指揮命令関係はなく、受託側は自分の裁量で業務を遂行することができます。仮に発注者が業務指示や人員配置の指定をおこないたいのであれば、業務委託契約ではなく労働者派遣契約を締結しなければなりません。これをおこなわず業務委託の形式のまま、発注者が受託者や従事者に対して具体的な指揮命令をおこなう行為は「偽装請負」とみなされます。
偽装請負が発覚した場合には、労働者派遣法や職業安定法に違反する行為として罰則が科される可能性があります。意図せず偽装請負の状態になることもあり得るため、企業としては業務委託と人材派遣の違いを正しく理解し、偽装請負と疑われるような行為は避けなければなりません。
偽装請負を回避する対策
企業が業務委託を活用する際には偽装請負にならないための対策が必要です。契約を締結する際は、業務委託につき発注者が指揮命令をおこなうことができないこと、従事者と雇用関係にある受託者に指揮命令権があることを契約書に明記しておきましょう。
また、就業中の指揮命令系統を明確にし、発注者が雇用する労働者と、業務委託を依頼する従事者が同じ場所で働く場合には特に注意しなければなりません。発注者から業務指示を受けることがないように従事者の座席を分ける、発注者の指揮命令下に置かれていないか定期的に現場の状況をヒアリングするなどの対策を講じ、契約上だけでなく実態としても偽装請負がおこなわれていないことを証明できるようにしましょう。
まとめ
業務委託契約には民法上の「請負」「委任」「準委任」の各契約があります。一般的にこれらを総称して「業務委託契約」と呼びますが、仕事の完成(成果物の納品)を対価に報酬が発生する請負契約に対し、委任(準委任)契約では業務の遂行に対して報酬が支払われます。一口に「業務委託契約」といっても、契約の種類によって法律のルールが変わる点に注意が必要です。
また、業務委託では発注者が受託側に対して指揮命令をおこなうことはできません。企業が業務委託を導入する際には、契約上は業務委託でありながら実態は労働者派遣となっている状況、いわゆる「偽装請負」を避けるための対策も必要となります。業務委託と人材派遣の違いを理解し、正しい方法で運用していくことが重要です。
導入実績800件以上!パソナのBPO・アウトソーシングサービスの特長
各業界に精通したコンサルタントが、 立ち上げから安定運用までお客様に寄り添い、様々なサービス形態を組み合わせたベストソリューションをご提案します。
立ち上げから安定運用まで
パソナのBPOサービス
お客様のニーズや課題に合わせて、オンサイト型業務委託(事業所内)・オフサイト型業務委託 (事業所外)を組み合わせ、経営資源をより高度な分野に集中できるようフルサポートします。