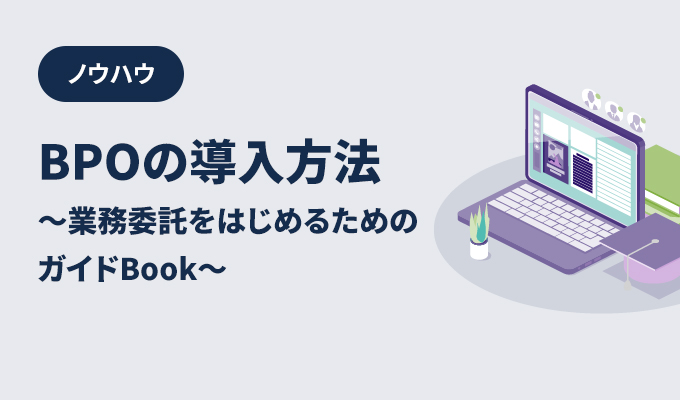おすすめ特集・コラムBPOとは?アウトソーシングとの違いやメリット・デメリット、会社選びのポイントを簡単に解説

更新日:2025.09.18
- BPO・アウトソーシング

BPOとは、自社の業務プロセスを外部企業に委託する手法です。外部の専門的なノウハウを活用することで、人手不足の解消や業務品質の向上などに効果がある一方、委託先での業務進行やデータ管理について把握しづらいという課題もあります。BPOを導入する際は、サービス会社の専門性や実績だけでなく、自社との連携やセキュリティ体制についても十分に確認しておくことが大切です。
今回はBPOについて解説し、アウトソーシングとの違いやメリット・デメリット、そしてサービス会社の選定を行うときに押さえておきたいポイントもあわせてご紹介します。
【業務改善についてお困りの担当者へ】
>>導入実績800件以上!パソナのBPO・アウトソーシングサービスはこちら
BPOの導入方法 ~業務委託をはじめるためのガイドBook~
近年、企業競争力の向上や経営基盤を強化するための有効な手段として注目されているBPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)は、業務プロセスの一部分を専門的な外部企業に委託する手法です。
- BPOの概要
- 導入時によくある課題
- BPOの導入ステップ~①既存業務の調査②BPOの可否判断③業務設計・運用準備~
- パソナのBPOサービスの強み
本資料では、BPOの概要や導入のプロセスについてご紹介します。
BPOとは
BPOとは「Business Process Outsourcing」(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)の略で、簡単に言うと「自社の業務プロセスを専門的な外部企業に委託する手法」のことです。「業務委託」という言葉を使うこともあります。
部署が担当している業務をまるごと委託する場合もあれば、業務のフローの見直しや最適な人材の配置プランなど、業務の効率化に向けた改善ポイントを提案してもらう場合もあります。専門的な知識やノウハウを持つプロフェッショナルに委託することで、自社の業務負担が軽減されるとともに、業務効率化や品質向上などさまざまな効果が期待できます。BPOをうまく導入すれば、自社のリソースをより付加価値の高いコア業務に集中させ、限られた経営資源をより戦略的に活用できるようになります。
なお、ニュースなどでよく話題になる放送用語のBPO(Broadcasting Ethics&Program Improvement Organization)は「放送倫理・番組向上機構」を指し、業務委託を意味するBPOとは全くの別物であることに注意が必要です。
BPOとアウトソーシングの違い


BPOはアウトソーシングの一種ですが、一般的に使われるアウトソーシングとは委託できる業務の範囲に違いがあります。
アウトソーシングとは、自社の業務の一部を切り出し、業務請負業者や人材派遣業者などに委託することをいいます。例えば、経理部門の経費精算業務のみを外部業者に依頼したり、人材派遣業者からスタッフを調達して作業を行ったりするイメージです。基本的には「特定の業務を遂行してもらうこと」を目的としたサービスであり、業務フロー全体の改善や仕組みづくりには関与しません。
一方、BPOはその業務にかかる業務フロー・システム・必要な人材の採用・教育含めて、まるごと外部に委託するサービスです。例えば、これまで経理部門が複数名で担当していた精算業務について、経費の申請フローから運用体制までのすべてのプロセスを委託先に委ねるようなイメージです。
つまり、アウトソーシングは特定の業務を任せる「限定的な業務委託」、BPOは業務全体を委ねる「包括的な業務委託」といえます。
アウトソーシングについてはこちらの記事もご参照ください。
関連記事:「アウトソーシングとは?メリット・デメリットや自社に適した種類、業務、導入の注意点を解説」
BPOとBPRの違い
BPRとは「Business Process Re-engineering」(ビジネスプロセス・リエンジニアリング)の略で、日本語では「業務改革」と訳されます。既存の業務プロセスを根本から見直し、抜本的に再構築することで、組織やビジネスの課題解決を図る手法です。
一方、BPOは業務プロセスそのものを外部に委託する手法であり、プロに任せることで業務効率化や品質向上につなげるアプローチです。BPRを推進する過程でBPOが活用されるケースも多く、BPRは業務改革という「目的」、BPOはその達成に向けた「手段」と位置づけられます。
関連記事:「BPRとは?意味や進め方から導入事例までわかりやすく解説」
BPOとITOの違い
ITOとは「Information Technology Outsourcing」(インフォメーション・テクノロジー・アウトソーシング)の略で、自社のIT関連業務を外部に委託することを指します。システムの企画から開発、運用まで一連の業務を委託できるサービスもあれば、社用パソコンの管理やヘルプデスクなど特定の業務のみを任せられるサービスもあります。
一方、BPOはIT分野に限らず、経理や人事など幅広い業務プロセスを包括的に委託できるサービスです。つまり、ITOはBPOの一部であり、対象範囲がIT業務に限定されるものが「ITO」と呼ばれています。
BPO導入を検討する企業が増えている理由
近年、多くの企業がBPOの導入を検討しており、その需要に伴って国内BPO市場規模も拡大傾向にあります。
2024年に矢野経済研究所が実施した調査によると、2023年度のBPOサービス全体(IT系BPOと非IT系BPOの合算値)の市場規模は、事業者売上高ベースで前年度比3.9%増の4兆8,849億2,000万円となっています。さらに、その後もBPOの市場規模は拡大し続けることが予測されています。

事業者売上高ベース
注2:IT系BPOとは発注企業からシステム運用管理業務を委託され代行するサービスとし、非IT系BPOとはその他の業務を委託され代行するサービスとする。
注3:2024年度以降は予測値
参照:株式会社矢野経済研究所 2024年調査 プレスリリース
経済産業省が提唱する「デジタルトランスフォーメーション(DX)」の進展により、企業間の競争が一層激しさを増すなか、限られた社内リソースをどのように配分して売上向上を目指すのか?といった「選択と集中の経営手法」が現代の経営に求められています。こうした背景から、外部に任せられるノンコア業務を切り出し、重要な意思決定を要するコア業務に社内リソースを集中する必要性がますます増しているのです。BPOは、限られた人材や時間を効率よく活用しながら、持続的な企業成長や競争力強化を実現する有効な手段となります。
また、企業がBPOを推進する目的には、人手不足の解消や働き方改革への対応なども考えられます。現時点で深刻なリソース不足に直面していない企業でも、今後ますます拍車がかかる人材不足を見据えて、今のうちから外部リソースを活用できる体制を整えておく動きが広がっているようです。
関連記事:人手不足な業界や職種は?背景と企業が取るべき対策とは?
BPO導入のメリット

BPOが注目されてきた背景や理由を解説してきましたが、ここで具体的なメリットについても解説します。
外部の専門的なノウハウを活用できる
部署では日々の業務に追われ、これまでのやり方を大きく変えたり、新たな業務に割く十分なリソースを確保したりすることが困難な状況も多くみられます。そうした状況下で、例えば、新しいシステムを短期間で導入し、新しい業務フローを推進することは簡単ではありません。
一方、BPO業者は特定の業務に特化しているため、専門的なノウハウを有するプロフェッショナルに業務を任せられます。例えば、RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)を活用すれば、従来は社内担当者が30分かけていた作業を1分で終わらせることができるかもしれません。RPAとは「ロボットによる業務の自動化」を意味し、人間がパソコンで行っている定型業務をロボットによって自動化する仕組みです。こうした外部ノウハウと自動化技術を活用することで、業務の効率化を図ることができるのです。
社内リソースの最適化
企業にとって、働き方改革は避けては通れない問題です。そのために“業務量が多い社員の負荷を減らし、業務の平準化を目指す”という目標を掲げ取り組んでいる企業もあります。しかし、日常的に発生する定型業務に社内リソースの大部分が取られ、企業が本来注力すべきコア業務(企業活動の根幹をなす業務。非定型的で高度な判断を必要とする)の人手が不足するようでは本末転倒です。
BPOを活用すれば、ノンコア業務(利益に直結しないが、企業のメイン業務遂行支援に必要な業務全般)や付随業務を外部に委託し、全体の業務量を削減できます。これにより、これまでノンコア業務に割かれていた社内リソースをコア業務や新規参入分野に集中できれば、戦略立案や意思決定といった付加価値の高い業務に力を注げるようになるでしょう。その結果、業務の平準化や効率化が進むとともに、売上向上や新たなビジネスチャンスの獲得につながることも期待できます。
人手不足の解消
BPOの導入は、多くの企業が直面している「人手不足」を解消するための有効な手段となります。社内リソースが限られるなか、本来の担当業務に加えて定型的な作業や付随業務まで抱えてしまい、利益に直結しないノンコア業務に多くの時間を取られるケースも少なくありません。こうした状況を解消するには、BPOを通じて人的リソースを補完し、社員が本来注力すべきコア業務に専念できる環境を整えることが重要です。
業務品質の向上、ミスの軽減
一つのことに特化したBPOサービス業者は、業務のフローが確立されています。これまでの業務フローのムダを省き、プロセスを明確に定義、整備されたマニュアルに則って業務が進むため、ミスも軽減され、高品質を維持することができます。
教育や設備投資のコストの削減
BPOを導入することで、教育費や設備費などのコストを削減できるメリットもあります。ノンコア業務を自社で抱える場合、その業務を担当する人材の採用・育成などの人件費に加え、システムの導入・維持といった設備投資も必要となります。
この点、BPOを活用すればノンコア業務にかかっていたコストをコア業務にシフトできるようになり、持続的な企業成長を支えるうえでも最適な戦略となり得ます。自社社員をコア業務に集中させることで、全体的なコストを抑えるだけでなく、さらなる売上向上を狙うことができるでしょう。短期的には委託費用が発生しますが、中長期的に見ればノンコア業務にかかる人件費や設備費の削減につながる「投資」となり、経営基盤の安定化や競争力強化にも寄与します。
BPO導入のデメリット
一方で、BPOの導入にはデメリットもあります。しかしデメリットの本質を理解することで、回避することが可能です。
管理、手法の可視化、社内ナレッジ構築の難しさ
業務フローを含めて委託してしまうため、その代行業者がデータをどのように管理し、どんなプロセスで業務を行っているのか可視化しづらいことがあります。そのため社員が現状を把握しづらく、社内ナレッジを構築することが難しいというデメリットがあります。しかしBPOを導入したあとも、運用の中で定期的に報告書を提出してもらうなどの契約をしておけば、業務がどのように進んでいるのか企業側で把握することも可能です。
初期費用がかかる
BPO導入時、運用フローの構築に、ヒアリング・業務調査、システムの構築、引き継ぎ、マニュアル作成などの導入コストがかかります。しかし業務が軌道にのり、委託する期間が長くなればなるほど経費とコストの差額で回収ができます。そのためにもサービス会社選びは慎重に行う必要があります。
セキュリティリスク
会社の機密情報を他社に開示するため、情報漏えいリスクの懸念があります。そのため、スタッフに個人情報保護研修を定期的に行っている、エビデンス管理体制が整っているなどセキュリティ対策が万全の委託業者、例えばプライバシーマークを取得している企業などを選択することが大切です。
関連記事:BPO・アウトソーシング導入のプロセスと、最大活用のためのポイント
BPOの3つの契約形態
BPOには「請負契約」「委任契約」「準委任契約」と呼ばれる3つの契約形態があります。どのような業務が対象となるのかをイメージしやすいよう、契約形態ごとの主な業務例を下表にまとめました。

請負契約
業務のすべてを委託し、成果物に対して報酬を支払う契約。
成果物に対してミスや欠陥が見つかった場合は、発注者は受託者に対し、瑕疵担保責任として責任追及を行うことができる。
(プログラミング・システム設計・ソフトウエア開発・デザインなど)
委任契約
法律に関する業務を委託する場合の契約。
(裁判の弁護・税理士の税務業務・不動産の契約書作成など)
準委任契約
「業務の処理」の対価として報酬を支払う契約。
成果物を債務完了基準としないため、瑕疵担保責任は問われないが、仕事の過程に対する責任として注意義務(善管注意義務)がある。
(給与計算・カスタマーセンター・事務業務など)
BPOの契約形態(請負契約・委任契約・準委任契約)については以下の記事でも詳しく解説しています。本記事とあわせて参考にしてください。
関連記事「業務委託とは?請負と委任・準委任の違いや契約時の注意点を詳しく解説 」
BPOを活用できる業務は多岐にわたる
BPOは、経理や人事、コールセンターなど多岐にわたる分野で活用できますが、すべての業務に適しているわけではありません。効果的に活用するには、BPOに向く業務と向かない業務を理解したうえで、自社の目的や状況に合わせて「どの業務を委託するか」を十分に検討することが重要です。
BPO導入に向いている業務内容
BPO導入の判断基準となるのが「コア業務」と「ノンコア業務」の区別です。
コア業務とは「企業活動の根幹を支える業務」を指し、企業の業績や成長を左右する中核的な活動をいいます。ルーティン化が困難な非定型業務であり、経営戦略の策定や製品の設計などがこれに当たります。一方、ノンコア業務とは「企業活動の補助的な業務」を指します。直接利益を生み出さないものの、円滑な企業運営に欠かせない業務であり、ルーティン化しやすいのが特徴です。
BPO導入に向いているのは、定型的で反復性の高い「ノンコア業務」です。下表を参考に、自社でBPOが可能な業務を検討してみてください。

BPO導入に向かない業務内容
BPOは幅広い業務に対応できるものの、高度な判断を要する「コア業務」には向きません。原則としてコア業務は内製化が適しており、外部に委託すると自社の独自性や競争力が失われるリスクがあります。そのため、戦略立案や製品開発、取引先との商談といったコア業務は自社で主体的に実施し、BPOはノンコア業務に限定して活用するのが望ましいでしょう。
関連記事:経理業務アウトソーシングのメリット・デメリットは?後悔しない選び方と成功事例をご紹介
BPOサービス会社を選ぶ時の5つのポイント
BPOサービス企業を選ぶときに、“これだけはおさえておきたい!”5つのポイントを紹介します。

1.専門性の有無
BPOサービス企業は、それぞれ得意な分野があります。例えば経理部門のBPOを発注するときに、システムの導入・構築を得意とする企業もあれば、経理業務全般のフローの構築を得意とする企業もあります。もちろん職種によっても得な分野は異なるため、その企業の専門領域については事前に確認しておきましょう。
2.受託会社の規模
従業員規模が数千名単位の企業が、少人数の企業に対してBPOを発注した場合はどうでしょうか。自社と委託先の企業規模に乖離がある場合、業務内容によっては委託先のリソース不足などで、本来想定していた業務運用が履行されない可能性が考えられます。委託先の企業規模が最適なのか、見極めて発注しましょう。
3.コンプライアンス・セキュリティ体制
委託内容によっては企業の内部情報を提供するため、委託会社のコンプライアンス、セキュリティ管理体制はしっかり確認して、BPOサービス企業を選ぶときの最優先事項としましょう。
4.予算
BPOを導入するメリットとしては、長期的に最適な運用が行われることで業務効率化が図られ、コストの削減につながることが挙げられます。BPOに対して最適な予算配分をするためには、委託検討先の提案が長期的な運用となっているのか、必要以上のサービスになっていないかを見極めることが大切です。適切な予算を確保し、予算に対して最適なソリューションを提供してくれる会社を選びましょう。
5.導入実績
自社が期待する業務委託の実績がある企業は、業務のフローやセキュリティ対策などが整えられ、知見があります。求めるサービスでの実績があるかどうか、確認しましょう。
パソナBPOサービスの具体的な導入事例

導入した企業がどのような成果をあげているのか、パソナのBPO・アウトソーシングサービスの導入事例をご紹介します。
事例1:経理事務BPO導入のシェアード会社
●課題
煩雑な経理事務業務のため人材が定着しにくく、指導や育成にも多くの工数がかかることが課題となっていました。さらに、正社員の負担が増大し、本来注力すべきコア業務に十分な時間を割けない状況が続いていました。
●施策
まず業務調査を実施し、属人化していた業務を可視化したうえで、段階的に処理フローを見直しました。さらに、業務の繁閑に応じてフルタイム勤務・短時間勤務・締め日前勤務など多様な働き方を導入し、全体の作業量を標準化しました。加えて、マニュアルの整備や新人教育体制の充実により、人材育成の仕組みを大幅に改善しました。
●成果
BPOの導入により、社員はコア業務へとシフトできるようになりました。さらに、業務量の変動に対応した運用体制によってコストの最適化・抑制を実現しています。加えて、新人教育体制の充実により、スタッフの定着率も向上しました。
事例2:一般事務BPO導入の生命保険会社
●課題
生命保険会社の一般事務では、複数ベンダーへの分散委託により業務の整合性が確保できず、継続的な運用に不安を抱える状況がありました。さらに、業務マニュアルが整備されておらず、標準的な業務処理プロセスやルールが不透明でした。また、新人スタッフの教育体制も不明確で、業務習得にバラつきが生じ、品質低下につながることも課題となっていました。
●施策
まず業務マニュアルやシステム操作手順を策定し、業務の標準化を徹底しました。ただ作成するだけでなく、メンバー間での周知・展開・共有を行い、現場への定着を図りました。さらに、新人研修のスケジュールやカリキュラムも体系的に整備し、策定したマニュアルを活用しました。加えて、ミス発生時の対応ルールも策定し、同様に周知・展開・共有を徹底しました。
●成果
BPO導入後は、マニュアル活用により業務の標準化と安定稼働を実現しました。また、新人教育の体系化によって進捗や習得状況を把握できるようになり、スキルや品質の検証体制の基盤が構築されました。さらに、ミス発生時の対応スピードが向上し、現場全体としてミス頻度の削減にも成功しています。
BPO導入事例企業インタビュー一覧はこちら:事務BPO/受発注BPO/カスタマーサポートBPO/派遣管理デスクサービス
~生産性向上策をギュッと解説!~ 総務部門のBPO事例紹介セミナー
総務の生産性向上を実現するBPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)導入の最新トレンドや、「何を、どこまでやってくれるのか?」や「自社にとって最適なBPO体制とは?」など事例紹介を交え、30分でギュッと分かりやすく解説しました。
パソナのBPOサービスの特長
4つの特長で展開し、豊富な実績を誇るパソナのBPO・アウトソーシングサービス。バランスの取れたサービス内容は多くの企業から支持されています。
特長1 専門コンサルタントが全面サポート
● 専門コンサルタントが業務調査、プロセス設計、体制構築、運用・改善まで伴走し、企業ごとの課題や業務特性に応じた最適なソリューションを提案します。
● 導入時には業務調査から可視化、ボトルネックの抽出、業務フローの設計・運用体制の構築まで丁寧に支援し、継続的な運用改善も責任を持って実行します。
特長2 ベストソリューションの提案
● 企業の状況やニーズに応じて、オンサイトBPO・オフサイトBPO・チーム派遣・クラウドソーシングなど多様なメニューから最適な体制・方法を提案します。
● 【国内BPO事業の実績案件1,000 以上・日本全国21拠点・16,000名以上のスタッフ】豊富な経験・ネットワークを活かし、戦略の立案から運営・レポーティングまで実行します。
特長3 専任のプロジェクトマネージャーが事業の運営を支援
● 各プロジェクトには専任のプロジェクトマネージャーを配置し、研修や情報共有を通じてサービス品質の維持・向上を図っています。
● さらに、BPO事業運営における人事制度と教育制度により、業務の属人化を防ぎ、サービスの品質を落とさない運営を可能にしています。
特長4 コスト削減・生産性向上に対応
● 業務の簡素化や重複削減による業務量の削減に加え、集約化・繁閑差への対応・自動化・RPA活用によって生産性を向上させ、単位時間当たりのコスト削減を実現しています。
● 運用開始後も継続的に品質を確保しながら、さらなる効率化とコスト削減を進めてまいります。
まとめ
BPOはアウトソーシングの一種であり、その業務にかかる業務フローやシステム、必要な人材の採用・教育も含めて、まるごと外部に委託できるサービスです。ルーティン化されたノンコア業務を外部に委託することで、自社の社員はより重要な判断を要するコア業務に集中できるようになり、新たな価値の創出や市場での競争力強化につながります。
パソナでは、1,000案件以上のBPO実績を持つ人材活用のプロフェッショナルとして、お客様の課題解決をフルサポートしています。パソナのBPOサービスについて詳しくまとめた資料をご用意していますので、BPOに興味のある方や導入をお考えの方はぜひご参照ください。